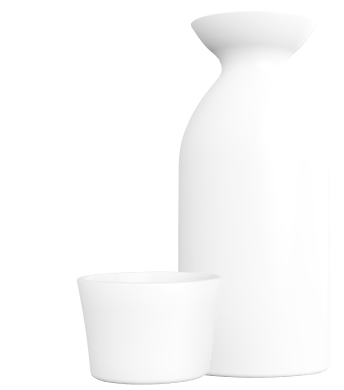お酒の情報が含まれますので、
20歳未満の方はご利用いただけません。
日本酒を知る
國酒でつむぐSDGs

神事を担い、人々の暮らしと共に歴史を経てきた國酒は、
つくり手の意欲と時代に則した刷新でSDGsに貢献します。
酒類業界におけるSDGsの取組み
歴史ある國酒のつくり手は、その知恵と工夫を未来に活かす

酒類業界では既に様々な
SDGsへの取り組みが進んでいます。
未成年者の飲酒防止や
アルコール健康障害発生の防止(SDGs項目③)
アルコール健康障害発生の防止(SDGs項目③)
酒類業界は20歳未満の者の飲酒防止対策など、酒税法の免許事業者として、社会的管理の要請に応えていく必要があることを十分に認識し、適正飲酒に向けた啓発活動に積極的に取り組んでいます。
酒類容器のリサイクル(SDGs項目⑫)
循環型社会の構築の観点から酒類容器等の3R(スリーアール)の推進に取り組んでおります。1.8ℓびんなどのリユースびんは、洗浄した後再利用されることでCO2の削減など環境に優しいリユース容器となっています。
食品廃棄物の発生抑制(SDGs項目⑫)
各地域社会に根差した原料調達に加え、酒粕、焼酎粕などの副産物の利活用により、廃棄物抑制を推進しています。

| ❶原料 | 土地土地の水や作物を原料に日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりんは醸されてきました。その土地で育てられたものを商品にしてお客様にご購入いただくことで地域の経済が循環します。 |
|---|---|
| ❷醸造工程 | 麹や酵母などの微生物の力を上手に利用して造られてきた日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん。製造工程における道具にも自然がうまく使われています。 |
| ❸副産物の利活用 | 製造工程で生まれる米糠や酒粕などの副産物は様々な形で利用されています。酒粕は焼酎、甘酒や粕汁などに利活用されています。 |
| ❹自然と共生 | 日本酒、本格焼酎・泡盛を製造するための水や作物は農業・酒造・地域の関係者が協力し合いながら守られています。 |
| ❺地域との共生 | 地域の原料を使い、地域の食に合う製品を造ることで地域に根差した酒類産業。様々な形で文化を形成し、地域社会に溶け込んでいます。 |
日本酒造組合中央会アンケート結果による
SDGs17項目各々の紹介
SDGs取組状況についてのアンケート調査
日本酒造組合中央会では、
SDGsについて日本洒造組合中央会の
組合員が行っている取り組みについて
現状を把握し、情報共有を図ることを目的に
アンケート調査を実施しました。
調査対象:組合員1,657事業者
(清酒、単式蒸留焼酎、みりん2種の製造業者)
調査方法:Google Forms、メール、FAX
実施期間:令和4年11月~令和5年1月
- アンケート
調査結果

SDGsに取組む酒造メーカー

酒類業界は従来より
環境に配慮してきた産業ですが、
今後も引き続きSDGsの取組を進めていきます。
また、企業としては各酒造メーカーの
状況に応じ、様々な形でSDGsへの
取組を進めています。
その具体的な内容は、各酒造メーカーが
ホームページ等により紹介しています。